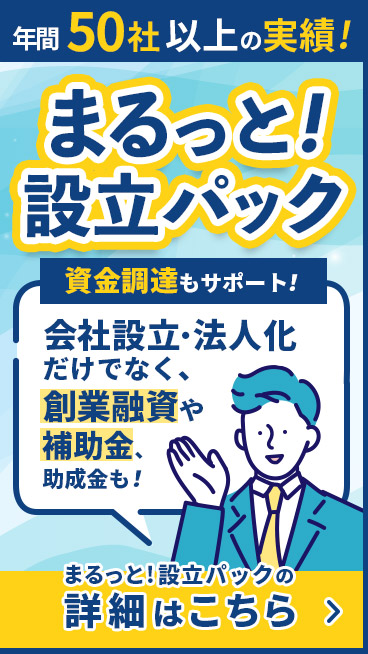今回は「税務調査が入る確率」について、個人・法人別に解説していきます!
「もし税務調査に入られたら大丈夫だろうか?」と不安に思ってはいませんか?
とくに初めての税務調査の場合、どのように対応すれば良いかわからないですし、追徴課税がどれくらいになるか未知数なので、ほとんどの方が不安を感じると思います。
そこで今回は、実際のところどれくらいの確率で税務調査に入られるのかについて解説していきます。
税務調査に入られやすい「職種」や「法人(個人)の特徴」なんかも解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
税務調査の種類

まず前提として、税務調査には大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
「任意調査」は、納税者の同意・協力のもとで実施される税務調査です。
実施されている税務調査の大半が「任意調査」で、多くの方が思い浮かべているものはこちらだと思います。
一方、「強制調査」はその名のとおり、事前告知なしで強制的に行われる税務調査のことです。
税法違反の疑いがある場合の税務調査で、裁判所から発行された許可状に基づいて実施されます。
確認の意味合いが強い任意調査に対し、違反を押さえに行くのが強制調査というイメージですね。
前提として、今回の記事では「任意調査」の方を対象として解説をしていきます。
税務調査が入る確率はどれくらい?
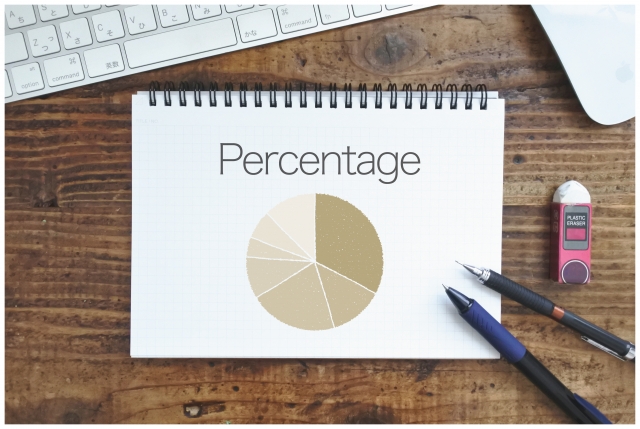
税務調査が入る確率は、あなたが以下のどれにあてはまるかによって変わってきます。
- 個人事業主
- 法人
- 個人(相続税)
それぞれどれくらいの確率で税務調査に入られるのか、1つずつ解説していきましょう。
個人事業主に税務調査が入る確率
個人事業主に税務調査が入る確率は、おおよそ0.5%~1.0%くらいです。
年度によって差はありますが、大体200年~100年に1回調査に入られる確率ですね。
決して高い数字ではなく、生涯で1度も税務調査に入られない事業主も当然います。
とはいえ絶対にあり得ない数字ではありませんし、税務署もランダムではなく怪しいところを中心に税務調査に入っているわけなので、「税務調査なんて来るわけがない」と高を括って適当な税務をすることは避けるべきでしょう。
法人に税務調査が入る確率
法人に税務調査が入る確率は、おおよそ1.5%~3%程度だと言われています。
個人事業主に比べると高くなりますが、それでも70年~30年に1度くらいの確率です。
なので当然、法人であっても1度も税務調査が来ないということは十分にあり得えます。
とはいえ個人事業主と同様、適当な税務や無理な節税(脱税)は避けるべきです。
個人(相続税)に税務調査が入る確率
事業を営んでいない個人であったとしても、相続を受けていた場合は10%前後の確率で税務調査に入られます。
個人事業主や法人と比べるとかなり高い数字ですね。
ここ数年(令和2年度~令和5年度)は新型コロナウイルスの影響などもあったことから3%~5%くらいで推移していますが、相続税の税務調査は申告から1~2年後に来ることが多いため、これから税務調査の確率がまた10%前後まで徐々に上がってくる可能性は高いと見込まれています。
とくに相続する財産が大きいと、その分税務調査に入られる確率も高くなるため、ここ数年で相続を受けている場合は心の準備をしておいた方が良いかもしれません。
税務調査が入る確率が高い業種

毎年、国税庁から「不正発見割合が高い10業種」と「不正(申告漏れ)所得金額が大きい10業種」が発表されており、これらの業種は税務調査に入られる確率が高いと言われています。
発表されている業種は、個人事業主、法人でそれぞれ以下のとおりです。
〇個人事業主
【事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得⾦額が高額な上位10業種】
- 経営コンサルタント
- ホステス、ホスト
- コンテンツ配信
- くず金卸売業
- ブリーダー
- 焼き鳥
- 太陽光発電
- 内科医
- スナック
- 西洋料理
※参考:「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」
〇法人
【不正発見割合の高い10業種(法人税)】
- バー・クラブ
- その他の飲食
- 外国料理
- 土木工事
- 美容
- 一般土木建築工事
- 職別土木建築工事
- 廃棄物処理
- 船舶
- その他の道路貨物運送
【不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税)】
- その他の化学工業製造
- 化粧品小売
- 物品賃貸
- 精密機械器具卸売
- 映画サービス
- 採石、砂・砂利採取
- 広告
- その他の卸売
- 外国料理
- 金属打抜き・プレス加工
※参考:「令和5事務年度法人税等の調査事績の概要」
これらの業種に当てはまる場合は税務調査の対象になりやすいと言えるので、より気を引き締めましょう。
税務調査が入る確率が高い個人事業主、法人の特徴

ここまで税務調査が入る確率を解説してきましたが、その確率は完全なランダムというわけではありません。
たとえば以下のような特徴がある個人事業主や法人は、税務調査に入られやすいです。
- 売上が急激に伸びた
- 売上の変動が大きい
- 同業他社と比較して利益率が低い
- 売上高が1,000万円にやや足りない
- 税務調査に入られやすい業種である
- 長期的に税務調査が入っていない
- 税理士が入っていない
逆を言えば、これらの特徴がなければ税務調査に入られる確率はさらに下がるということです。
1つずつ解説していくのでチェックしてみてください。
特徴1.「売上が急激に伸びた」
急激な売上の伸びがあった場合、税務調査の対象になる可能性は高まります。
事業の実態にそぐわない、不自然な増収を疑われるからです。
また一気に売上が上がったことで申告漏れが起こりやすく、その際に取れる追徴課税も大きくなりやすいという理由もあります。
あとは、急激な売上増は単純に目立つため、調査官の目に留まりやすいというのもありますね。
特徴2.「売上の変動が大きい」
毎年の売上の変動が大きい場合も、税務調査の対象になりやすくなります。
「売上を不正に調整しているのではないか」と疑われるからです。
もちろん事業の特性や状況、景気、時流の流れによって売上が変動することは調査官もわかっています。
しかし、「それにしても変動が大きい」と調査官に思われた場合は、税務調査の対象になる確率が高くなるでしょう。
特徴3.「同業他社と比較して利益率が低い」
同業他社と比較して利益率が低い場合、税務調査に入られる確率が上がります。
売上高に対して利益があまりに少ないと、不正な経費計上が行われているのではないかと疑われるからです。
また利益が低すぎると、「事業者はどうやって生活しているのか?」という観点からも疑いを受けてしまいます。
特徴4.「売上高が1,000万円にやや足りない」
もしあなたが消費税の免税事業者であった場合、売上高が1,000万円にやや足りない状態であれば税務調査の確率は高まります。
売上高1,000万円が課税事業者にならなければいけないラインであるため、消費税の納税を逃れるために不正に売上を抑えているのではないかと疑われるからです。
たとえば無申告の売上がある、不正な経費計上がある、などの不正ですね。
とくに1,000万円にやや足りない売上高が続いている場合は、調査官にマークされる確率は大きく上がるでしょう。
特徴5.「税務調査に入られやすい業種である」
あなたの事業が「税務調査が入る確率が高い業種」で挙げたものと同じ、もしくは近しいものであった場合、税務調査に入られる確率は上がります。
対策できるような理由ではありませんが、とくに税務には気を付けるようにしましょう。
特徴6.「長期的に税務調査が入っていない」
長年事業を続けているがまだ税務調査が入っていないというケースも、税務調査に入られる確率が上がります。
もちろん、一生税務調査が入らない事業者もいますが、しかし本当であれば、全事業者の税務調査に入って、正しい税務が行われているか定期的に確認できるのが税務署としての理想です。
そのため、長年税務調査に入られていない事業者は優先的に調査対象に選ばれると考えられます。
「ずっと税務調査が来ていないから大丈夫」とは考えず、年々来る確率は上がっていると考えておくべきでしょう。
特徴7.「税理士が入っていない」
確定申告を税理士に依頼せず、自分でやっている場合も税務調査の対象になりやすくなります。
税理士が入らず素人が確定申告をやっていると、当然ミスが起こる確率が高くなるからです。
というより、税理士が入っていない事業者の確定申告は高確率でミスがあるとさえ言われています。
そのため税務署としても、しっかり調査して徴税したいと考えるわけですね。
税務調査が入った時の対応方法

税務調査が入ったら、基本的には調査官の指示に従って対応することになります。
税務調査(任意調査)の主な流れは以下のとおりです。
- 事前通知が来る(現金商売の場合は通知がない場合もあり)
- 税務調査の日程を決める
- 当日の調査に立ち会う(調査官の質問に応答する)
- 税務署による調査が行われる
- 税務調査の結果が出る
- 必要に応じて修正申告、追徴課税の納税を行う
その際、以下のポイントについてはしっかりと押さえておきましょう。
- すぐ税理士に連絡する
- 帳簿類をしっかり整理しておく
- いらないことは言わないように注意
税務調査が入った時のために、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
すぐ税理士に連絡する
顧問税理士がいる場合は、通知があった時点ですぐに顧問税理士に連絡を取ってください。
基本、税務調査の連絡は税理士を通して行われますが、直接納税者に連絡が来ることもあり得ます。
当然ですが税務、経理については税理士の方が詳しいので、資料の用意や当日の立ち合いなど対応してもらいましょう。
帳簿類をしっかり整理しておく
税務調査の当日、調査官の質問に対応できるように帳簿類はしっかり整理し、すぐに見せられる状態にしておきましょう。
とくに用意しておいた方が良いのは以下の書類です。
- 法人税申告書(個人事業主は所得税の申告書)
- 決算書
- 登記簿謄本
- 総勘定元帳(帳簿)
- 売掛、買掛帳
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 預金通帳
- 棚卸明細表
- 源泉徴収簿
- 給与台帳
- 領収書の控え
- 納品書
- 請求書
- 契約書
- 稟議書
- 議事録
これらの資料をすべて提出するわけではなく、調査官から一部の提出を求められるので、その際にさっと該当資料を見つけ出して渡せるようにしておいてください。
ちなみに税務調査で見られる期間は過去3年分のケースが多いですが、場合によっては5年分、7年分と延びるので、法廷保存期間内の資料はすべて用意しておきましょう。
いらないことは言わないように注意
税務調査でいらないことを言うと、思わぬところで疑いを持たれてしまう可能性があるので注意です。
調査官は会話の矛盾点から、調査対象が嘘を言っていないか見極めます。
たとえば、趣味を聞かれて「ゴルフです」と答えたケースだと、領収書を見てゴルフ接待の経費が多ければ、「これは仕事に関係のない趣味のお金なのでは?」と疑われることになるわけです。
調査官も会話の中でそういった情報を引き出そうとしてくるので、いらないことは言わないように注意しつつ、真摯に応対しましょう。
税務調査に入られる確率を下げる対策

税務調査に入られる確率を少しでも下げたいなら、以下のような対策をおすすめします。
- 正確な記帳、適切な経理管理、適切な税務申告を行う
- 申告や記帳を税理士に依頼する
- 意図的な不正は行わない
もちろん、これらを徹底しても税務調査が来るケースはあります。
しかし普通に考えれば、「納期遅れや記載ミスなどで適切な税務ができていない」、「素人が申告や記帳をしている」、「不正を疑われるような痕跡がある」というケースと比べれば、税務調査が入る確率は大きく下げられるはずです。
税理士がいれば税務調査は安心……とは限らない

税理士がいれば税務調査に入られる確率は下げられますし、税務調査が入ったとしても立ち会ってもらえます。
しかし、税理士がいれば必ずしも安心とは限りません。
なぜなら税理士によって、税務調査時の対応が大きく異なるからです。
たとえば、いざ税務調査に入られた時に、下記のような税理士であったら安心できますか?
- 連絡してもレスポンスが遅く返信がなかなか返って来ない
- 税務調査のアドバイスをしてくれない
- 調査官に言われるがままで交渉してくれない
おそらく「本当に大丈夫なのか?」と疑ってしまうのではないでしょうか。
残念ながら、このような税理士も少なくないのが現実です。
その点、私たち池上会計はクイックレスポンスを強みとしている会計事務所なので、税務調査の通知が来たのに返信がなかなか返って来ない……とヤキモキさせることはありません。
また、私たちは事前に、
- 税務調査とはどんなものなのか
- どんな進め方をするのか
- どんな書類を準備すればよいのか
- 調査官はどんな質問をしてきて、どう受け答えをすればよいのか
など、あなたの会社の特徴をもとに整理して、豊富な経験から社長や経理担当者にレクチャーさせていただきます。
そのうえでもちろん、立ち合い時にもしっかりと対応します。
税務調査に入られにくくなる対策も行っているので、もし「税務調査が不安」、「今の税理士がほとんど対応してくれない」などあれば、ぜひ1度無料でご相談ください。
【まとめ】税務調査が入る確率は下げられる
今回は税務調査に入られる確率について解説をしてきました。
傾向をまとめると、個人事業主でおおよそ0.5%~1.0%、法人で1.5%~3%程度、個人(相続税)で10%前後が税務調査に入られる確率です。
ただこれは、業種や事業者の特徴などによっても変わってきます。
基本的にそこまで高くない数字ですが、「うちには来ないだろう」と高を括っていると痛い目をみるかもしれません。
一方で、普段からしっかりと税務を行っていれば、税務調査の時に安心できるのはもちろん、税務調査に入られる確率を下げることにも繋がります。
税務調査の確率は低いからと油断せず、普段からしっかりと備えておくことが大切です。